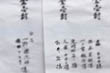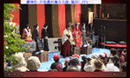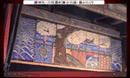-

デコ回しメドレー 
- 那賀町・川俣農村舞台. 木偶回し・箱回し.
| Microsoft Edge を、お使いの方は、HTML文書の読み上げ機能が使えます、右はその使い方です。 |

- [場 所]: 礫神社境内
- [公演 日時]: (平成27年度以降は公演をしていないようです)
- 川俣農村舞台は、長安ダムの下流にある橋を渡り、通称、古屋谷川を遡って行きます、但し、公演当日は、桜谷トンネルの西口にある貯木場から、シャトルバスが出ます、川俣農村舞台には、駐車場は有りません。
- 川俣農村舞台の、建築年は1879年(明治12年)だそうです。
- 明治中期に、泥絵の具で描かれた襖絵(唐紙)は、8枚が1組で、95枚現存し、町指定、有形民俗文化財だそうです。
- 舞台は間口9.68メートル、奥行き5.8メートルの、切妻造りで、向かって右側に、太夫座があります。
- 戦後、娯楽の多様化と共に、他の農村舞台同様に廃れ、使用されなかったが、1965(昭和40)年に、地元の人たちによって、舞台は復活したそうです。
- 1991(平成3年)年12月7日、全国的な民芸ブームの影響も有ったのでしょう、40年ぶりに人形芝居公演が復活したそうです。
- お問い合わせ ■那賀町役場、上那賀支所、地域振興室
那賀町、川俣、ドウノ前4、川俣農村舞台
電話、0884-660111、
■那賀町教育委員会
TEL:0884-62-1106、
 川俣農村舞台の場所
川俣農村舞台の場所- 長安ダムの手前、やく200メートルの所にある橋で、那賀川を渡り、古屋谷川を遡っていくと、約20分で川俣に着きます。
- 道は狭く、カーブが多いから気をつけて運転してください。
- 但し、公演当日は、駐車場が少ないため、シャトルバスが出ます、車では行かないように。 行っても駐車場はありません。
- クリックすれば「GooGle」の地図がポップアップしますから、拡大縮小して確認してください。
-
第3回川俣農村舞台公演、演目
- 阿波木偶、箱回し保存会の「木偶回し」「箱回し」
- 加茂町・ゴンサキ 楽器、ジャンベの演奏
- 桜谷小学校「歌」
- 丹生谷清流座「三番叟」
- 川俣農村舞台保存会 「襖からくり・御花披露」
- もち投げも有りました。
- その他、木偶回し、箱回し)
- 「木偶回し」、「箱回し」は、徳島県西部を中心に、お正月の祝福芸、門付け芸として長く行われてきた物です。
- 大分前ですが、NHKのドキュメンタリー番組で、女性が師匠につき、箱回しの技術習得に励んでいると言う番組を見たことがあります。
- このページのビデオで先ず、デコ回しの雰囲気だけでも味わってください。
- 阿波木偶、箱回し、保存会の人から、門付けをしていた人の孫が、学校で「えべっさんの子」、「ものもらいの子」等と、からかわれ、孫から「えべっさん」、やめて、と言われ、孫かわいさから以後、門付けをやめていた、と言うお話を聞きました。
- 福を分け与え、五穀豊穣、大漁祈願、家内安全を、呼ぶ芸が、からかわれ、差別された歴史、が有ったとは残念なことだと思います。
- 三好市、イヤ地方で昔から食べられていた物に、デコ回しと言うのがあります。
- 人形浄瑠璃の「デコ回し」が、食べ物の「デコ回し」の語源になったようです。
西アフリカの歌、マライカ。
多分、こんな形で、ご披露してくれます-法市農村舞台の場合

- 私は、昭和48年から2年6ヶ月、当時は、未だ上那賀町小浜、と言われていた所に住んでいたことがあります。
- 古屋、川俣、谷山には知人が居ましたので良く行きましたので、神社があることは知っていましたが、その当時、農村舞台の事が話題になることはありませんでした。
- 今回、初めて川俣農村舞台の公演を見に行きました。
- 午前11時頃、桜谷トンネルを抜けると、何人かの法被を着た方が案内に立っていました、誘導に従って駐車場に入りました。
- すでに駐車場は満車状態になっていたので、随分たくさん来ているなと驚きました。
- 暫くしたらシャトルバスが出たのでそれに乗り、会場へ行きました。

礫神社と川俣農村舞台と周辺の様子
礫神社までの様子、長安ダム、深森付近、神社境内、お花披露など。
礫神社までの様子、長安ダム、深森付近、神社境内、お花披露など。
川俣農村舞台の舞台公演、襖カラクリ、
- 襖は、明治中期に、泥絵の具で、描かれたそうで、現在、8枚が1組で95枚残っているそうです。
- 戦後は、ほとんど上演されなかったそうですが、1965(昭和40)年になって、久しぶりに地元の人たちによって再現されたそうです。
川俣農村舞台公演・特別出演・その他、
- 最初の人は今までに何度か、ここで公演されたことがあるようでした。
- 桜谷小学校の子供の中に、私の知り合いの子供がいましたので、帰宅後プリントして送ってあげました。
- 私の子供も、1年生の時だけ通っていました、その後、転出しましたが懐かしい所です。
残念ながら、桜谷小学校は、平成26年度の卒業生をもって、閉校になったと言うことです。

川俣農村舞台のビデオ
- 杉木立の中
- 三番叟、箱回し
- デコ回し、箱回し、傾城阿波の鳴門、安珍清姫メドレー
- 川俣農村舞台の襖からくり、
阿波「木偶回し」、「箱廻し」について
- 徳島の人形浄瑠璃芝居は、幕末から明治にかけ、全盛期を迎えました。箱廻しは、芝居小屋や農村舞台で演じられた『絵本太功記』や『傾城阿波の鳴門』などの人気外題を、路傍で簡易に演じた大道芸です。
- 箱廻し芸人は、2人か3人が一組になり、ふたつの木箱に、数体の木偶を入れ、天秤棒で担いで、全国を移動し稼ぎました。数体の木偶を一人で操りながら浄瑠璃を語ります。
- 全国の農山村に、阿淡系の木偶文化を運び、各地の人形芝居に大きな影響をあたえました。
- ひとびとに親しまれた「箱廻し」は、昭和初期に街角から姿を消しました。
- しかし、祝福芸の「三番叟まわし」は、一部の地方で、伝承され現在は、阿波木偶、箱廻し、を復活する会が伝承し、元旦から旧正月が明けるひと月余りで、約900軒余りの民家で門付けしています。
- 2011年の元旦には、「ゆく年、くる年」(NHK)で紹介されました。
「阿波木偶、箱まわし保存会」のホームページから引用しました。
娯楽性豊かな、伝統芸能で農村舞台にはピッタリだな思います。
Copyright (C) 2020 [JH5OZI] All Rights Reserved、
コンテンツの転載引用は、悪意が無い物に限り、ご自由です。