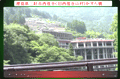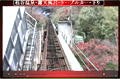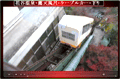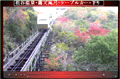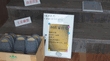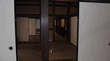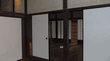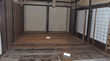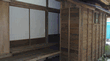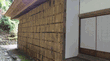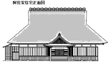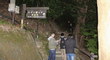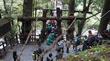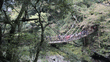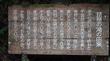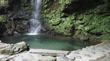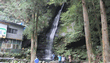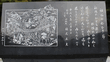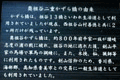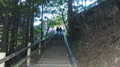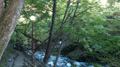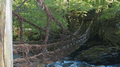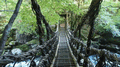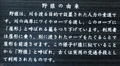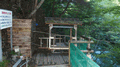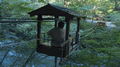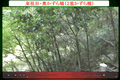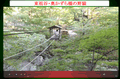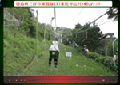- 秘境 祖谷.平家伝説 ケーブルカー.露天風呂 剣山リフト.錦秋の祖谷
-
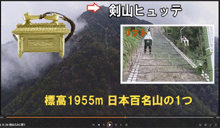
剣山リフト上空と、

祖谷の語源、意味
- 「祖谷」と言う地名について、柳田國男は、“祖谷”、“オヤ”は、元は、祖霊の、います地、という意味を持ち、後にその意味に合った 漢字を当てはめた、とする説をとなえています。
- この「祖谷」という音は、”祖(おや)”の語源だそうで、「祖=親」が“敬(うやま)われる対象”だった、事に依るとされています。
- また地方の方言に、「祖谷さま」(=叔父)と言う地方があるそうで、叔父さんも尊称の対象です。
- その他に、祖谷を「祖谷」と読む理由が判然としませんが、書き方は別として、「祖谷」の音に注目すれば、 イ(井)・ヤ(谷)で、川の流れる谷、という意味になると言う話もあります。
祖谷のカズラ橋は、錦帯橋、猿橋と共に、日本3大奇矯の1つです。
- カズラ橋は、祖谷地方に、かっては6カ所ほど有ったそうですが、現在では、東祖谷に1箇所、西祖谷山に1カ所、残っているだけです、
その内、東祖谷のカズラ橋を「奥カズラ橋」、又は「2重かずら橋」、と呼んでいます。
- かずら橋の由来は、
祖谷に巡行された弘法大師が、川を渡るのに難渋して困っている、村人の為に作った、という説や、追っ手から逃れる、平家の落人が、楽に切り落とせるように、蔦をよりあわせてて作った、という説など、諸説が残っています。
- 300年以上続く伝統あるかずら橋です。

西祖谷のかずら橋のビデオです
- ビデオは、3年に1度、2月に行われる掛け替え工事中のかずら橋で、前回の物です。
- 付近には雪が残っていました。
- 秋のカズラ橋です、祭日だったので多くの人が来ていました。
- カズラ橋の架かる祖谷川の少し上流にある琵琶の滝です。 平家の落人が都を偲び、滝の側で琵琶を奏でたのでこの名が付いていると言うことだそうです

「阿佐家住宅」県指定有形文化財
、三好市歴史的風致維持向上施設、
、三好市歴史的風致維持向上施設、
- 阿佐家の主屋は、この地域の一般的な農家で見られる、オモテにあたる部屋がなく、式台玄関を、設けるなど、山間の上層農家の典型例、として貴重で、平成12年3月21日付けで、徳島県の有形文化財として指定されました。主屋の建立は、棟札より文久2年(1862年)だそうです。
- 経年変化、台風による屋根の破損等、建物全体に破損が進行し、関係機関での協議が重ねられ、根本的な保存修理をしました。
- 同時に主屋を三好市の所有に替えて、管理をしているそうです。
- 現在無料で一般公開されています。

西祖谷のかずら橋
- カズラ橋と周辺の写真(スライド)です。
- カズラ橋は3年に一度、シラクチカズラという蔦を使って掛け替えられます。

露天風呂へ向かう、祖谷温泉の夕闇のケーブルカーなど。
祖谷川沿い、祖谷温泉の「源泉かけ流し露天風呂」。
平家伝説の東祖谷山村、奥カズラ橋と野猿の位置
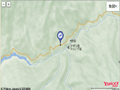
奥カズラ橋と、野猿
- 国道32号の、大歩危道の駅から「奥カズラ橋」までの案内です。
- 国道33号線から、剣山に向かって車で、約40キロ、所要時間は1時間ぐらいです。
- 10月から11月までは、紅葉で賑わいます。
- 道は、そんなに悪くはありません。

東祖谷カズラ橋(奥かずら橋、夫婦橋)の写真
九州の椎葉村と、祖谷の平家伝説

- 壇ノ浦の戦い後、二位尼は死を決意して、幼い安徳天皇を抱き寄せ、宝剣を腰にさし、神璽を抱えた。
- 安徳天皇が「どこへ行くのか」と仰ぎ見れば、二位尼は「弥陀の浄土へ参りましょう。波の下にも都がございます(波の下にも都のさぶらふぞ)」と答えて、安徳天皇とともに海に身を投じました。
『吾妻鏡』によると二位尼が宝剣と神璽を持って入水、按察使局(あぜちのつぼね)が安徳天皇を抱いて入水したとあり、続いて建礼門院ら平氏一門の女たちも次々と海に身を投げたとの事です。 - それでも、平家の女官の多くが、源氏の兵に救助されたそうですが、女官は遊女等にならざるを得ませんでしたが、安徳帝の命日には、女官は斎戒沐浴し、安徳帝の冥福を祈ったそうです。
- これが今日でも、毎年5月に下関赤間神宮で ”先帝祭上臈参拝” として行われています。
これが、下関最大のまつりの ”しものせき海峡まつり” です、私は九州の椎葉平家祭りで、見た事が有ります、外八文字の大変優雅なものでした、右上の写真をご参考に。
椎葉平家祭り右上の写真の祭りです。
- この戦いで平氏は政治勢力としては滅亡したが、一門そのものは断絶することなく、その後も続いているそうです。
- 後に鎌倉時代初期、伊勢国と伊賀国で平家の残党が起こした三日平氏の乱など、平家の落人が存在した事自体は間違いないようですが、元々が逃亡、潜伏した者であるため、歴史学的に客観的な検証が可能なものは少ないのだそうです。
- 平家一門の人が無事逃れ、連綿として続いていると言うのは、お話としてはロマンがあり、面白いですが、多くが文字通り伝説伝承のようです。 祖谷の平家伝説については私は良く知りません、平家屋敷と言うのが有りますが、明確に根拠づける物は無かったと思います。
- 剣山に10戒を記した石板を入れた、アーク(聖櫃)が有るとか、有った等と言う、荒唐無稽な話が有ります、古事記、日本書紀、邪馬台国まで引っ張り出し、都合の良い様に切り継ぎしたお話のようです、ピラミッドは宇宙人が作った、と言う話と変わらないようです。 面白いを通り越して、奇想天外と言うところでしょうか?
Copyright (C) 2018 [JH5OZI] All Rights Reserved
コンテンツの転載引用は悪意が無い物に限りご自由です