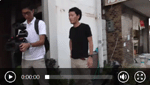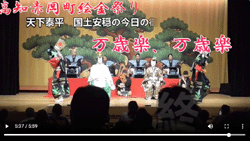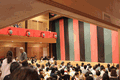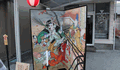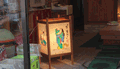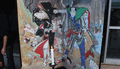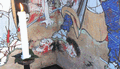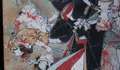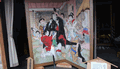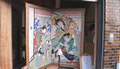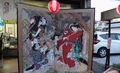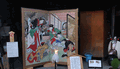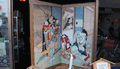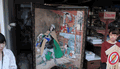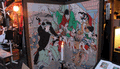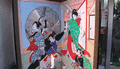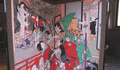-

絵きん屏風ビデオ 
- 土佐、赤岡 絵きん祭り
| Microsoft Edge を、お使いの方は、HTML文書の読み上げ機能が使えます、右はその使い方です。 |
土佐、赤岡、絵きん祭り会場
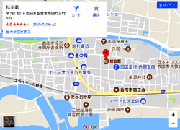
会場付近の地図
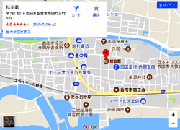
会場付近の地図
- 高知県、香南市、赤岡町本町・横町商店街で行われます。
- 高知空港から東へ、県道14号を、約3キロメートル行くと、案内の看板があります。
- 絵きんとは、幕末から明治にかけて、土佐で活躍した、町絵師「広瀬きん蔵」のことです。
- 人々は、絵師きん蔵、を略して「絵きん」、と呼びました。
- 絵きんは、その才能が認められ、江戸、狩野派で修行し、藩のお抱え絵師となりましたが、贋作の罪に問われ、職を失い、城下を追放されたそうです。
- その後、赤岡に住まいを移し、町絵師として、人々の求めに応じ、当時人気の高かった「芝居絵」を描き、その才能を発揮しました。 その絵きんが描いた、屏風絵などが赤岡町に、残っており、それを展示するように、なったそうです。
- 絵金蔵に所蔵する絵師・金蔵が描いた芝居絵屏風・18点の修理を2019年から行っていましたが、令和4年4月14日このほど修理が完了したそうです。
- 修理された芝居絵屏風は、今年10月の、絵金生誕210年に合わせて、公開される予定だそうです。
土佐・赤岡・絵きん祭り
- 【日 時】、(毎年7月第3土、日) 令和7年7月19日(土)、20日(日)
- 【場所】 高知県、香南市、赤岡町、本町、横町商店街
- 【主催】 土佐、赤岡絵きん祭り、実行委員会(香南市商工会内)
- 【問い合わせ】 香南市商工会、
- 【主な催し】
- 絵きん蔵に、一番近い駐車場、徒歩 3分 香南市、商工会、駐車場
- 障害者様として、絵きん蔵の北側入口、絵きん蔵、身障者用、駐車場(2台) ※一般の方の、ご利用はご遠慮ください、、

18時〜21時
土佐、赤岡、絵きん祭り、実行委員会、
0887-54-3014、
-
路上解説、絵きん屏風
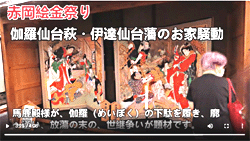
路上解説ビデオ
絵きん祭りの間、地元有志により、平成5年から、芝居小屋「弁天座」にて上演されます。
【駐車場について】
(バス 2台/一般車 10台)、
※カーナビゲーションシステムをご利用の場合は
0887−54−3014、香南市商工会、に設定されると便利です。
(と、なっていたが、既に関係の無い車が1台停まっていた)
(標章の掲示が無かった、何処でも、こう言うのが居るものです)
- 私は徳島ですが、私の嫁さんが、高知県、奈半利出身で、よさこい踊りと、「絵きん」は、前から知っていました。
- よさこい踊りは、毎年見に来ていますが、「絵きん」は、今回、初めて見に来ました、予想していたのとは違って、かなり盛大でした。
- 絵きんとは(詳しく) 弘瀬 きん蔵(1812年11月4日)〜 明治9年(1876年)3月8日)は、江戸時代から明治にかけての、浮世絵師の事です。高知県下では広く「絵きん」と呼ばれている。
- 高知城下、新市町に髪結い職人の子、として生まれ、姓は木村氏。後に医家某の、嗣子となって弘瀬を名乗る。 幼少から、絵の才能で評判となり、16歳で江戸に行き、土佐江戸藩邸御用絵師や、幕府御用絵師、狩野洞益に師事した、とも言わている。
- しかし、狩野探幽の贋作を、描いた疑いを掛けられ、高知城下所払い、の処分を受け、狩野派からは破門された。 洞意(絵きん)が実際に、贋作を描いたか、どうかは明らかでは無く、習作として模写したものが、商人に渡り、若くして御用絵師になった洞意(絵きん)に対する嫉妬から、濡れ衣を着せられた、と洞意を擁護する意見も、有るそうです。
- 高知城下を離れた後、叔母を頼って赤岡町(現・香南市)に定住し、「町絵師、きん蔵」を名乗り、地元民から頼まれるままに、芝居絵や絵馬、凧絵などを、多数描き「絵きん」の名で親しまれた。 この時期の、土俗的で血みどろの、芝居絵は、特に評判が高く、現在も赤岡では、毎年7月に、屏風絵を展示する「土佐赤岡絵きん祭り」が行われています。
10年かかる、とされる修行期間を3、年で修了し、林 洞意(はやし とうい)の名を得て、高知に帰郷、土佐藩家老、桐間家の御用絵師となる。
Copyright (C) 2018 、[JH5OZI] All Rights Reserved、
コンテンツの、転載引用は、悪意が無い物に限り、ご自由です。